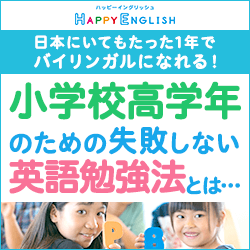2020年始めに突如現れた新型コロナウイルス。生活が一変しました。
Ozzbyが勤務する会社では2020年2月に都内で一人感染者が報告された日の翌日から在宅勤務に。お客様との面談もすべてをOnlineで対応するようになりました。
あれから早2年半。オンラインでの面談も定着。大手企業の多くもオフィスの縮小化が進んでいるようすです。
実は、Ozzbyの会社は2021年11月をもってオフィスを完全になくしてバーチャル企業にしました。2020年の夏に完成したばかりの新オフィスは未使用のままClose。新調したオフィス家具は全く使われないまま解体されて廃棄となりました😭
このオフィス撤退プロジェクト・・・実はものすごく色々な問題があり結構苦労しました💦
今後、バーチャル化も進むについれて似たような体験をされる方もいらっしゃるかと思うので覚えているうちに書き留めておこうと思います(と下書きにしてから投稿まで既に一年近くたってしまいましたが(笑)
決めないといけないこと
Table of Contents
- 住所
- 電話
- Fax
- サーバーの管理
- 書籍などの管理体制
- オフィス撤退にあたり家具・荷物の処分
- 社員への対応について
- クライアントへの案内で大変だったこと・・・
① 登記には住所が必要
日本では法人の登記が必要で必ず住所登録が必要です。そして役所関係はもちろんですが、健康保険組合や銀行など一定の書類は登記簿上の住所にしか送付してくれなかったりします。
在宅勤務になってからずっと総務担当が会社宛ての郵便物は各担当者宅に転送。
会社として必要な書類は、総務→社長宅→会計士→(対応後 必要に応じて)→Ozbby→ 社員という3~5 steps。かなりの時間とお金の無駄でした。
今回かなり大変だったのはこの住所。色々迷った結果Ozbbyの会社では、以下の2つにわけて住所を決定することにしました
(a) 登記簿上の住所
(b) 業務用の住所
(a)の登記簿上には前述の複雑なステップをなくすために会計士と社長が使う住所に。契約書以外で使うことがない住所。
(b)は外部とのコミュニケーション用。お客様とのやり取りや社員が業務上必要な書類を社長側に配布してしまうと紛失してしまうケースが考えられるため・・・
1つは業務連絡上に使える都内の住所が必要ということで、バーチャルオフィスサービスを探すことにしました。
結局、信頼性とサービスの充実度(コロナ後のことも考えて)わが社では外資の老舗の1つであるServcorpを使うことにしましたが、、、これはかなり色々調べてからの決定事項。長い道のりでした、、、、
【バーチャルオフィス・サービスを決める時のチェックリスト】
- 信頼性:ポッと出のサービスも多々あります。郵便物を預かってもらうのでここは信頼度が必要。また、何度も住所を変えるのは避けたいので運営会社の規模なども考慮して決定
- 提供住所のエリア :24区内でも今までは千代田区・新宿区・港区・品川区・中央区に絞ってリサーチ
- 機密保持体制がしっかりしているか:大事な書類も届きますので、その内容をしっかり秘密保持して対応してもらうことが大事です。企業によってはここが結構曖昧なところもあったので要注意です!
- 郵便物の転送頻度・費用:各社あまり大差なし。
Ozbbyの会社ではそれまでの在宅勤務期間でできるだけ定期購読の雑誌はストップし、業者さんからの書類もEmailで対応してもらえるよう変更したので届くのはほぼJunk。ただ、、、どうしても紙の書類が必要なこともあるのでこのサービスは必須でした。
毎日来ている郵便物は知りたいけれど、転送は1週間に1回程度を予定しています。 - レンタル会議室などの有無、設備:バーチャル化といっても今後の社会情勢が変われば再度オフィスを設けたり、チーム会議をしたり、お客様との会議などを行う場所もほしい。必要な時に毎回会議室を探すのは手間なので、会議室も借りれる場所にしました。
以上を考慮して数件ほど調べましたが、最終的にServcorpやRegusの大手2社に絞られて、その時の営業対応の印象でServcorpに決定。
今後また海外出張が復活したら、海外にも拠点があるので出張中にも打合せ場所として使えます!(そんな日がまたくるのかなぁ??)
郵便物が届かないようにする工夫も必須!
住所を外部に提示すると必ずそこに郵便物は届いてしまう、、、できるだけ郵便物の転送費を削減するためにも、WebsiteやEmailの署名欄には「バーチャルオフィス」であることをしっかり明記し外部にも理解をしてもらうことを始めました。
弊社では全社員が在宅勤務しております。上記住所に弊社スタッフは在中しておりませんことをご留意ください。代表電話は限られた人数での対応となっておりますため繋がりにくくなっております。ご連絡の際はお手数ですが、お問合せフォームからお願いいたします。なお、営業のお電話や郵送物はご遠慮頂けますようお願いいたします。
<次>第2弾は電話とFaxについて